2025.10.31タイムレスな子供の教育
【第2回】AI時代を生き抜く-AIに「使われる人」と「使いこなす人」-【文京区・新宿区のプログラミング教室講師の解説】

こんにちは、タイムレスエデュケーションの鈴木です。文京区や新宿区の教室で子どもたちを見ていると、同じ課題に取り組んでいても、「自分で考えて行動する子」と、「言われたことを待つ子」に分かれています。まだAIを直接使う機会は少なくても、すでにその姿勢の違いが、将来AIを“使いこなす側”か“使われる側”かを分ける兆しになっています。今回はそんな二つの未来をテーマに記事を書かせていただきました。ぜひご覧ください。
AIに「使われる人」「使いこなす人」──残酷なまでに分かれる二つの未来
前回の記事では、AIの進化によって、社会や企業が求めるスキルが根本的に変わり始めている現実についてお話ししました。それは、今の子どもたちが社会に出る頃には、さらに加速しているであろう大きな変化の波です。この変化の中で生き抜くために、単なる知識だけでなく「論理的思考力」や「創造力」といった力が、子どもにとって欠かせないものになりつつあります。
では、この変化の中で、子どもたちの未来はどのように変わっていくのでしょうか。それは、すべての仕事がAIに奪われるという単純な話ではありません。むしろ、人間が「AIとどう関わるか」によって、その役割が大きく二つに分かれていく、という未来です。今回は、これからの社会で生まれるであろう「二つの未来」の姿と、その未来を分ける決定的な違いについて、詳しくお話ししていきます。
未来の働き方(1):AIに「使われる人」

一つ目の未来は、AIに「使われる」働き方です。AIが社会に浸透すると、多くの「判断」や「指示」はAIが担うようになっていきます。金融では、市場分析や与信審査をAIが一瞬でこなすようになり、人間の役割はその結果に沿って処理や承認を進める形にシフトしつつあります。商社やメーカーでも、AIが需要予測や物流計画を立て、社員はそのシナリオに基づいて業務を進めるケースが増えていくでしょう。公務員も、行政システムが判断した内容を画面に表示し、それを住民に伝える場面が増えると考えられます。その結果、AIが設計したシステムの中で、AIに「使われる」働き方は、
- AIが出した判断や指示をもとに、定型的な処理や確認作業を行う
- AIが判断できない、ごく例外的な事態に対応する
などといった、限定的な役割に集約されていきます。このように、「AIが出した結論を前提に動く”働き方”」が広がれば、自分の意思や創造力を発揮する場面は限られます。仕事がなくなるわけではありませんが、代替可能性が高まり、やりがいや成長の機会が得にくい働き方になってしまうリスクは無視できません。
未来の働き方(2):AIを「使いこなす人」
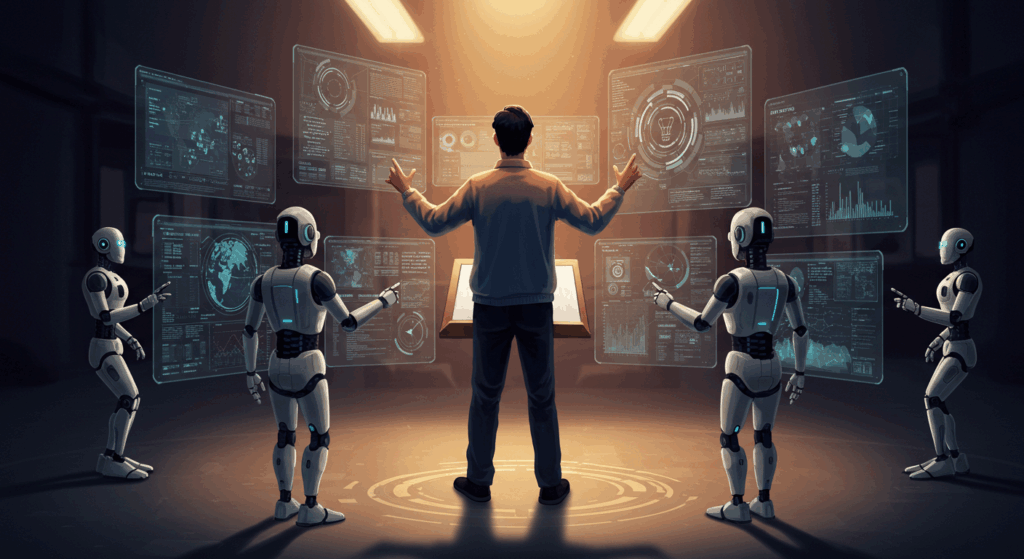
二つ目の未来は、AIを「使いこなす」働き方です。こちらでは、AIを脅威ではなく、自分の能力を何倍にも高めるパートナーと捉えます。金融であれば、AIが示すデータを参考にしつつ、顧客ごとの事情に応じた提案を考える。商社なら、AIが示す市場データや需給予測を踏まえながら、現地の政治情勢や文化的背景、人との信頼関係までを考慮し、どこにチャンスがあるかを見極めて動く。公務員なら、AIが導く標準的な解決策に地域特性や市民の声を組み合わせ、新しい施策を生み出す。
共通しているのは、AIを「答えを出す機械」ではなく、「考える力を引き出す道具」として使っている点です。AIの答えを鵜呑みにせず、「なぜ?」「もっと良い方法は?」と問いを立て、自分の頭で考え抜く。その過程で論理的思考力と創造力が働き、既存の枠を超えた新しい価値を生み出します。
こうした力は、今の子どもたちが将来どんな仕事をするにしても強力な武器になります。この二つの未来の間には、仕事のやりがいだけでなく、将来的な収入においても、無視できない大きな格差が生まれるであろうことは、想像に難くありません。
未来を分ける、たった一つの能力
では、「使われる人」と「使いこなす人」を分ける、決定的な違いとは一体何なのでしょうか。それは、
AIに自分の考えを的確に伝え、AIの答えをもとに自ら考えを深め、磨いていける力
です。差を生むのは、専門知識の“量”や学歴の“高さ”そのものではありません。AIに「正しく考えさせる」ために、その知識を「どう使うか」、そして「使い方を自分で考えられるか」が重要な土台になります。目的を明確にし、要素を整理し、条件を具体化して指示を出す──そのプロセスこそが、『論理的思考力』であり、最初のステップです。
しかし、そこからが本当のスタートです。AIが出した結果を鵜呑みにするのではなく、「なぜこうなったのか?」「別の視点ではどう見えるか?」と問い直しながら、自分の思考で磨いていく。時にはAIの出した「あり得ない答え」が、まったく新しい発想のきっかけになることもあります。重要なのは、結果を否定することではなく、「なぜそう出たのか」から学び、視点を広げる姿勢です。これが『創造力』です。
AIを使いこなす人とは、AIの能力を使って思考を深め、アイデアを鍛え上げ、自分なりの答えを生み出せる人のこと。そしてそれは、今の子どもたちが社会に出たとき、どんな仕事にも通じる“生きる力”になるのです。
ここで、一つ分かりやすい例を見てみましょう。今話題の文章生成AI(ChatGPTなど)に、「物語を創ってもらう」というお願いをするとします。
【曖昧な指示(使われる側の発想)】
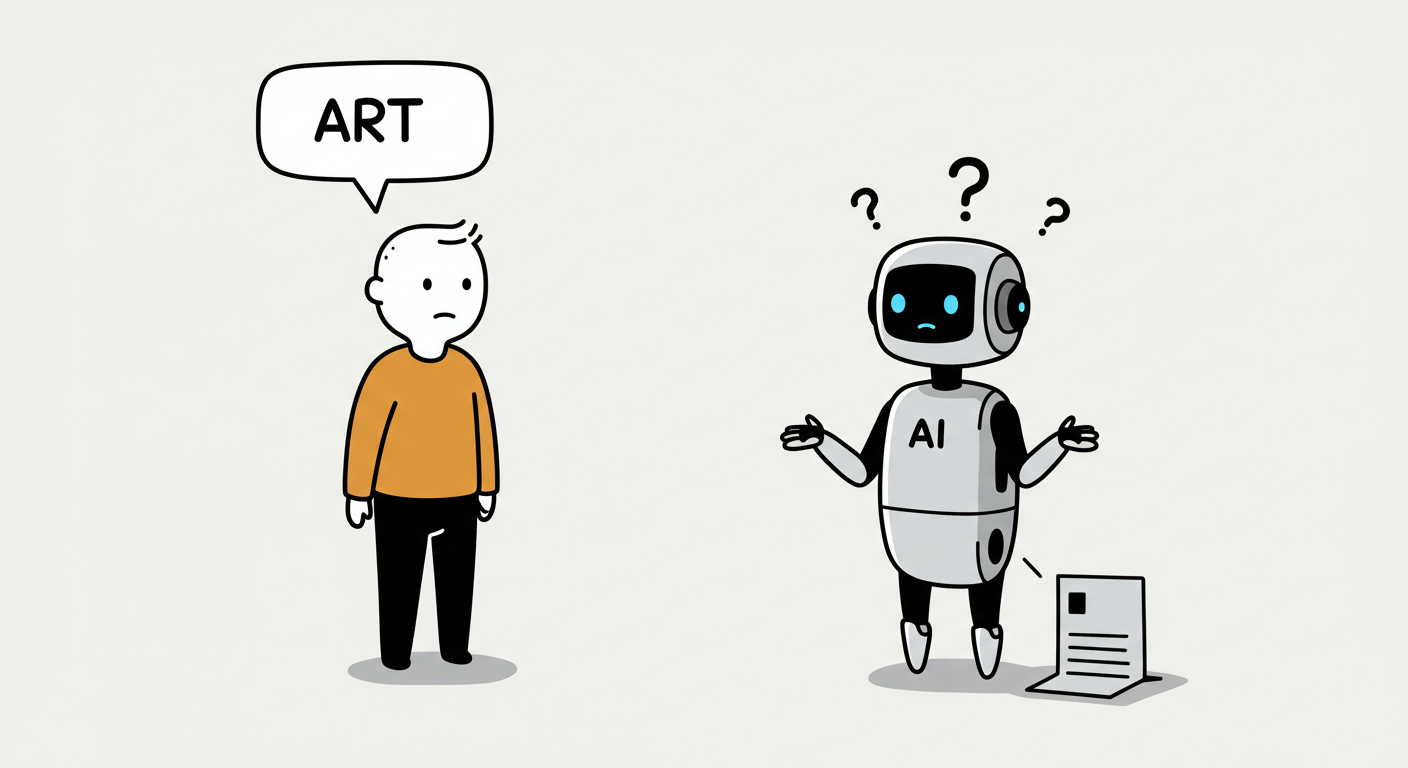
「面白い物語を書いて」
この指示では、AIは過去に学習したデータの中から、最も「ありきたり」で「無難」な物語を生成するしかありません。誰にでも作れる、価値の低いアウトプットです。AIに仕事を丸投げし、その性能に依存してしまっている状態です。
【的確な指示(使いこなす側の発想)】
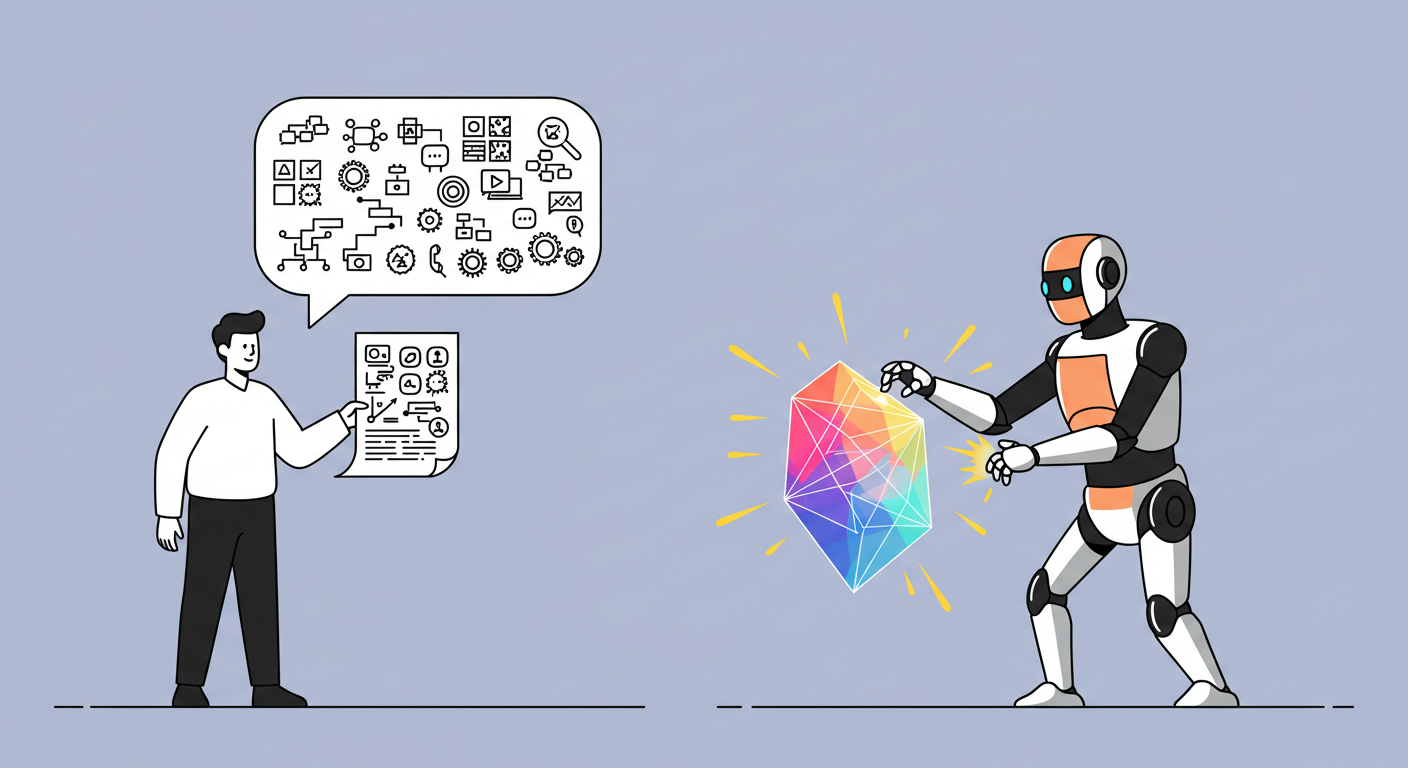
「内気な小学生が、時間を超えて未来の自分と対話できる不思議なコマを手に入れる。その対話を通じて、少しずつ自信を取り戻していく成長物語を、小学生にも分かる平易な言葉で、全3章構成で書いて。第1章は出会い、第2章は葛藤、第3章は成長をテーマにしてください」
この指示を受け取ったAIは、書き手の意図を汲んだ物語の“たたき台”を生成します。そこから「展開が単調ではないか」「もっと感情の動きを描けるか」と問いを重ね、内容を磨いていく。このやり取りの中に、まさに“AIを使いこなす”思考プロセスがあります。
後者の「的確な指示」には、
- 目的が明確(主人公が自信を取り戻す)
- 要素が分解されている(登場人物、道具、テーマ設定)
- 順序が指定されている(全3章の構成)
- 条件が具体的(小学生にも分かる言葉で)
といった、目的を明確にし、要素を分解し、順序を整理するという「論理的思考力」が反映されています。さらに、AIの回答を吟味しながら新たな発想を加えていく過程には、「創造力」が働いています。これこそが、AIを「使いこなす」ための本質であり、今の子どもたちに最も育んでほしい力なのです。
その力は、どうすれば育まれるのか
では、この「自分の考えを的確に伝え、考えを深めていく力」、すなわち「論理的思考力」や「創造力」は、特別な才能なのでしょうか?
いいえ、違います。
実は、大人たちが、子ども時代に夢中になった「あの遊び」の中に、この力を育むすべてのヒントが隠されています。次回は、多くの方が驚かれるであろう、その意外な繋がりに迫ります。ぜひ次回もご覧ください。
最後に
タイムレスエデュケーションは、文京区茗荷谷・本駒込・千駄木、新宿区下落合を拠点に、「考える」「創る」「伝える」力を育む小中高生向けプログラミング教室です。当教室はお子さまが「誰にも奪われない強み」を見つけ、自分の意思で未来を選べるようになるための教室です。毎回の授業で「探究→創造→発信」をくり返す構造化カリキュラムを通じて、「論理的思考力」「表現力・創造力」を育みます。秋の無料体験会も開催致しますので、ご興味のある方はぜひお申し込みください。心よりお待ちしております。

